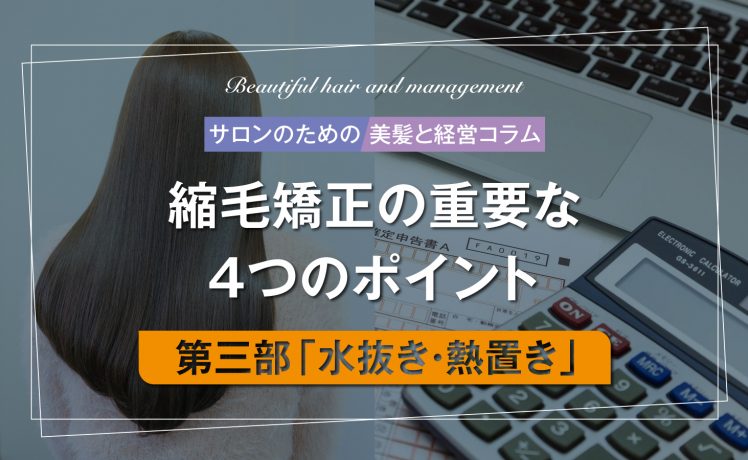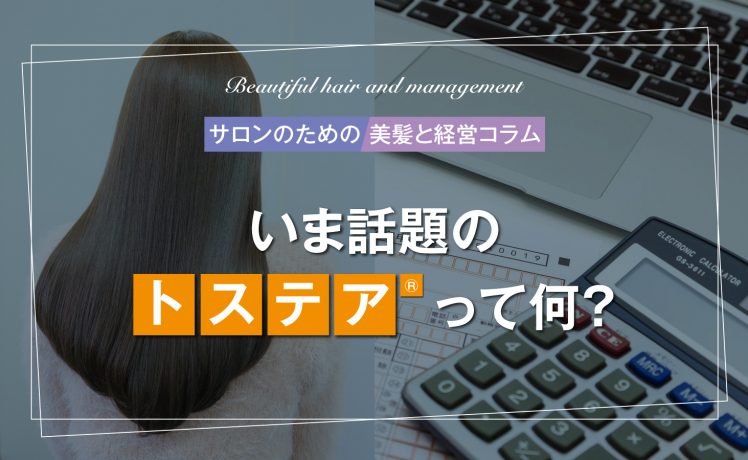オンナゴコロのくすぐりドコロ 第5回:コンセプトが伝わるネーミング

この原稿を、神戸発のお茶のブランドの「ムレナスティー」を飲みながら書いています。この紅茶は、友人同士でよく贈りあうのですが、その理由はパッケージとネーミング。ストロベリー、ラズベリー、ブルーベリーを調合した紅茶の名前は「パステル色のおたんじょう日」。「おたんじょう日の紅茶」とでかでかと金色の文字で箱にプリントしてあるので、お誕生日の人に渡すのに、ちょうどよいのです。パッケージも華やかで、キッチンに置いておきたくなる可愛さ。
カスタードバニラの香りのお茶には「ミックスフルーツアラモード」という名前とともに、「いつも前向きでありたいのですの紅茶」と書いてあります。これも、落ち込んでいる友人に、プレゼントしてあげたくなるネーミング。
「元気出して!」と言葉で伝えるのは押しつけがましく思えてしまっても、紅茶のパッケージに書いてあるのはさりげなくて、ちょうどよい。
こんな風に、一歩先まで消費者のことを考えている「コンセプトが伝わるネーミング」「用途まで提案しているネーミング」「思わず人に伝えたくなるネーミング」はうまくハマると、商品ヒットの強い追い風になってくれるのではないでしょうか。
ただの商品の説明にとどまらず、わかりやすさをより一層追究したもの、コンセプトを誰もがわかりやすいような言葉で置き換えたもの、擬音語や擬態語をまぜてインパクトを持たせたもの。そういった商品名は、人の頭に残りやすく口の端にのりやすいのです。
食べ物なんかは特にわかりやすくて、「煮込みスープ」よりも「じっくりコトコト煮込んだスープ」、「鹿児島産の芋」よりも「生キャラメルいも」のほうが、それぞれ美味しそうに感じられますよね。(※いずれも実在する商品名です)語感が面白かったり、新鮮に感じられると、SNSにも載せたくなります。
ビジネスでネーミングが売り上げを変えた例は枚挙にいとまがなく、「モイスチャーティシュ」は「鼻セレブ」、「粘着カーペットクリーナー」は「コロコロ」にしてから、売上数がぐっと上がったとか。
私も、「辛そうで辛くない少し辛いラー油」や「風に吹かれて豆腐屋ジョニー」「マスカルポーネのようなナチュラルとうふ」「濃密ギリシャヨーグルトパルテノ」など、商品名にひかれて購入することは数知れず。時間に追われる現代だからこそ、数秒でイメージをぱっと湧かせられる商品名が持つ役割はますます大きくなっているはずです。
「人は見た目が9割」という本が数年前に大ベストセラーになり、最近は「伝え方が9割」という本も、大ヒットしました。商品が星の数ほどある時代に、商品の「質」「見た目」にこだわるのは当然のこと。その上で、「伝え方」はどうなのかが改めて問われる時代なんですね。
ただ長いだけやインパクトがあるだけではなく、商品の特徴やその先の消費者の利用シーンをイメージするところに、ネーミングの正解があるように思います。